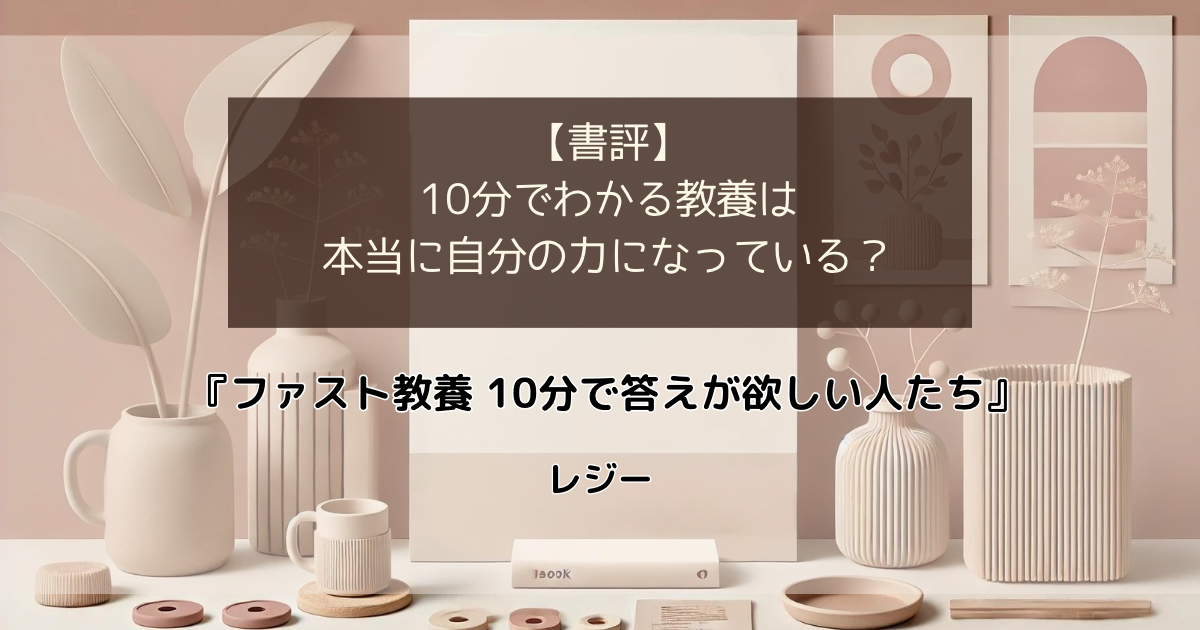「社会人こそ教養を身につけよう」とよく聞きます。
学び直しやリスキリングと並んで関心が高いキーワードですね。
私自身、「社会人としてある程度の教養は身につけておいた方がいいよね」と考えていました。
しかし、『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』というタイトルをみて、ちょっとドキッとしました。
「ファスト」とか「10分で答えが欲しい」とか、ズバリ言い当てられた感じ。
自分の考える「教養」は、「=ビジネススキル」になっていないか?
『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』は、現代の情報消費社会における「ファスト教養」という現象を鋭く分析した一冊です。
著者のレジー氏が、ビジネスパーソンが手軽に知識を得ようとする風潮と、その背景にある社会的要因を深く掘り下げています。
ビジネススキルの獲得は、社会人として避けて通れないものです。
しかし、「ファスト教養」を追い求め、本当に必要なものを手放していないでしょうか?
一度立ち止まって「教養」の本質について考えるために、この本を読んでみることをおすすめします。
興味を持ったらAudible(オーディブル)でチェック
『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』は、Audible(オーディブル)の聞き放題対象作品。
耳で聴けるオーディオブックなら、通勤中など手が離せない時でも読むことができます。
初めて利用する人は30日間の無料体験が提供されるので、興味を持ったらまずはAudibleでチェックがおすすめです。
『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』の概要
本書では、YouTubeやビジネス書などで得られる「すぐに役立つ」知識や教養を「ファスト教養」と定義しています。
そして、「ファスト教養」が求められるようになった背景や、その影響について述べています。
「ファスト教養」の否定ではなく、知っておいた方がいいデメリット部分にスポットが当たっている本です。
- 有名なビジネス系インフルエンサーたちの提供する「ファスト教養」的コンテンツを対象ごとに細かく分析。
- 焦りや不安を抱えるビジネスパーソンたちがどのように受け入れているのかを検証。
- ファスト教養が社会全体に及ぼす影響や、その価値観が日本社会にどのように浸透しているかを考察
ビジネスのために「ファスト教養」と定義されるコンテンツを利用している人も、よりよい活用法を知るためにぜひチェックしておいてほしい一冊です。
この本を読んで学べること
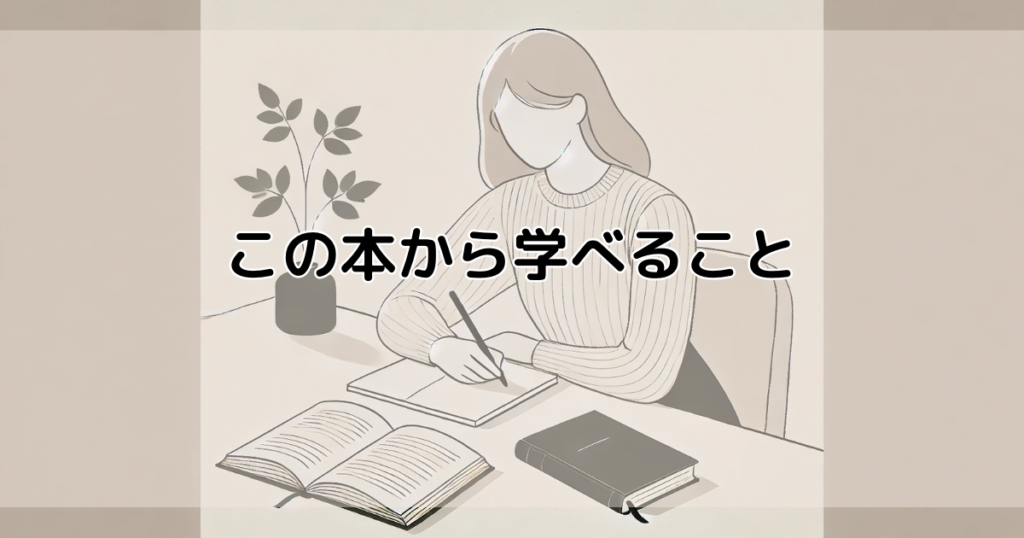
この本では、大きく以下の3つを学べます。
①「ファスト教養」の特徴
「ファスト教養」とは?
著者が「ファストフード」をもじってつけた名称です。
短時間で手軽に摂取できる状態の知識=ざっくり全体を把握できれば表面的な情報でOK、な風潮を指します。
この傾向は特にビジネスパーソンに強いようです。
情報過多で求められる能力が多い現代、ビジネスパーソンは「意味がある」より「役にたつ」を求めています。
「ビジネスの場ですぐに使える知識を持っていること」が教養とされているのです。
ファスト教養のメリット・デメリット
・情報処理のスピードUP
・得た知識がさらに深く学ぶきっかけになる
・情報処理が早いので余剰時間が増える
・「わかったつもり」になる
・自分なりの原理原則に落とし込めない
・無意識に「教養のない人」を見下してしまう
「スピーディに情報処理をすること」と「教養」は、あまり相性がよくないようです。
なぜ「ファスト教養」が広がった?
「ファスト教養」が広がった背景には、自己責任論に端を発する不安がある、と著者は分析しています。
2000年代前半、小泉内閣のもと新自由主義にもとづく「自由と自律(≒自己責任)」を重視した政策が進められました。
その結果、
- 自分の身は自分で守る、他人は放っておけ
- 過去の経緯や慣習で特定の人だけが利益を得るのはやめるべき
- 成功=お金をたくさん稼ぐことである
こういった社会的な空気が出来上がりました。
その空気感の中で育ってきた世代が、いわゆるビジネス系インフルエンサーとして個人でお金を稼いで生き残るための「ファスト教養」を普及するようになりました。
②ビジネス系インフルエンサーの役割と影響
ビジネス系インフルエンサーの役割とは?
ビジネス系インフルエンサーは、複雑な情報や専門的な知識を短時間で理解できるように要約し、視聴者に発信しています。
彼らは、YouTubeやSNSなどのプラットフォームを活用し、ビジネス書の要約や自己啓発のメッセージを発信することで、多くのフォロワーを獲得しています。
多くのビジネスパーソンが「自己責任論」の空気の中で、「自分でお金を稼がなくちゃ!」と焦っているので、こういった発信を活用します。
「ファスト教養」の発信がひとつのビジネスモデルとなっているんですよね。
ビジネス系インフルエンサーの影響は?
しかし、発信される情報を鵜呑みにする危険性も指摘されています。
情報の取捨選択や解釈がインフルエンサーの主観に依存するため、偏った情報になったり、インフルエンサー自身の影響力が強まることで、情報の受け手が自ら考える機会を失い、受動的な情報受容者になるリスクも考えられます。
つまり、本来の教養の本来の目的「自分で思考する力」を持つことが難しくなり、問題解決能力や創造性の低下を招く可能性があるのです。
インフルエンサーたちは、あくまで求められる情報を「ビジネス」として発信しています。
情報を消費する視聴者が「ファスト教養」を求めている限り、発信側がリスクに対して責任を負ってくれるわけではないことを覚えておく必要があります。
③「ファスト教養」の影響と解毒方法
「ファスト教養」が与える影響
「ファスト教養」が与える影響として、以下が挙げられています。
- 知識の浅薄化:情報を短時間で消費することで、知識が表面的になり、深い理解や批判的思考が育ちにくくなる
- 思考の短絡化:簡潔な情報に慣れることで、物事を深く考える習慣が失われ、思考が短絡的になる
- 文化の消費主義化:映画・音楽など文化的コンテンツも効率的に消費され、作品の本質的価値が軽視される
本来「ノイズ」として思考を強化・拡張してくれるはずの文化的コンテンツを効率的に消費するようになったことが指摘されています。
本のあらすじだけをチェック、映画を倍速視聴する、など、心当たりのある人もいるのでは。
「教養」で得られるのが効率化された情報だけ、では豊かな社会が作れるとは思えませんよね。
「ファスト教養」をどう解毒する?
多かれ少なかれ、ビジネスパーソンの意識に刷り込まれた「ファスト教養」的な思考。
著者は「ファスト教養」を全否定しているわけではなく、「適度に摂取」をすすめています。
適度に摂取するために、
- 先に結論を決めることなく、思考のノイズになるものも取り入れる
- 手軽さ・わかりやすさ・情報の正確性が両立し、「入門の先に広がる世界の深さ」も見せてくれるコンテンツを選ぶ
こういったことを意識して「ファスト教養」に向き合おう、と主張しています。
本を読んだ感想と変化
「教養」はあった方がいい。
本書を読んだ後もその気持ちは変わりませんが、「手軽に得られる知識」に満足するリスクについて考えるようになりました。
シンプルでノイズのない「情報」は、飲み込みやすいけれど、自分なりの「原理原則」が身につかない。
そして、中途半端にファスト教養を摂取すると、無意識に他人にマウント意識を持ったりする状態に陥りかねない。
これは「教養のある」振る舞いではない、と考えます。
「自分の頭で考える」ための教養を、コスパを重視して取り込むのはちょっと違うな、と再認識。
ジャンルを問わずたくさんの本を読んだ時、思いもよらない考えが繋がる瞬間があります。
これは効率重視の知識からは生まれない思考だと思います。
「未知のものへの畏れや例外的な出来事への配慮」「違う立場に対する想像力や思いやり」を養う、教養本来の意味を忘れず、「ファスト教養」をうまく使いたいですね。
『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』で「教養」を見つめ直そう
『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』は、現代の情報社会における「ファスト教養」という現象を鋭く分析し、その背景や影響、そして私たちがどのように向き合うべきかを考察した本です。
効率的な情報収集が求められる時代だからこそ、深い思考や多様な視点を持つことの重要性を教えてくれます。
ビジネスパーソンや自己啓発に関心のある方、現代の情報社会に疑問を感じている人におすすめの1冊です。
合わせて読みたい
ビジネスパーソンがじっくり「教養」を得られなくなった背景を、さらに深く掘り下げて解説している1冊。
文化的なコンテンツから得られる「ノイズ」のこともわかりやすく書かれています。
合わせて読むとさらに理解が深まります。
こちらの記事で書評をしているので、よかったら参考にしてみて下さい。
-

-
【書評】ベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』から読書を学ぶ
2025/1/26 三宅香帆